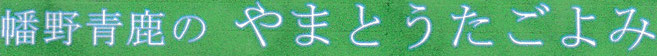「あとがき」などを読む
歌に寄せて
私の親族には、父方にも母方にも何人かの広島の被爆者がいます。市中心部に住んでいた父方の曽祖母については、その最期を知る手掛かりも遺骨や遺品も、一切ありません。爆心地近くの官庁に勤めていた母の従姉も、また同様です。私自身も、最後の世代の被爆二世です。そうした出自などもあって、先の大戦や被爆に関する様々な事柄には、この街の人間として人並みか、それ以上に目を向けてきたつもりです。一方で、幼い頃に見聞きした惨状が今もトラウマになっていて、話がむごたらしい描写に及ぶと最後まで正視できず、その事をずっと負い目に感じてきました。
そんな中、令和6(2024)年の長崎原爆の日を目前にして、ひとつの報道が耳に入ってきました。
それは、長崎の平和式典に駐日イスラエル大使を招待しなかった長崎市に対して、日本を除くG7諸国等の駐日大使が連名で書簡を送り、式典への参加を取りやめたというものです。今も日々続くガザ地区での大量殺戮などまるで無かったかのような「強者」の言説に、被爆地の人間として私は二重三重の憤りとやるせなさを覚えました。その悶々とした気持ちを抱えていた8月9日の朝、長歌の形をした「あの日」に関するたくさんの言葉が、私の元に次々と湧き出てきました。
私は普段、自然を主題にやまとことばのみを用いて古語を交えた短歌や長歌を詠んでいます。長歌が出来る際はいつもこんな風に、思ってもみない時に五・七・五・七…の長歌の形で、たくさんの言葉が溢れてくるのです。やまとうたという韻文のことばは、散文に比べてひとつひとつが強い力を持っています。被爆についての強い負のエネルギーを持ったことば達が、雪のように私の上に降ってくる時間は、苦しく心塞がるものでした。とはいえ、ことばに携わる者には、与えられたことばを放り投げて捨て去るという選択肢はあり得ません。
肩にのしかかる黒い影に心を打ちのめされながら、長歌のことばをひとつひとつ何とか仕上げてはみたものの、私は頭を抱えてしまいました。被爆の実相は、写真や絵画を含めて多くの記録に残されています。被爆者によって書かれた散文や詩などの原爆文学も、少なからずあります。被爆者の方が自身の声で語る証言に勝るメッセージは、この世界にありません。その一方で、惨状を見ていない私が詠んだこの取っ付きにくい歌が一体誰に届き、何の意味を持つのだろう、と。被爆者の方からは「あの日の現実はそんな甘いもんじゃない。実相も知らずに分かったような口を利くな」と言われても仕方ないでしょう。
だとしても、ジャーナリストにはジャーナリストなりの、作家には作家なりの言葉の用い方があるように、歌に憑かれた私にはこのようなことばの紡ぎ方しかできません。もし私に繋がる亡き被爆者たちがこの歌を聞いたとしても怒ったりはしないだろう、このことばが犠牲者の霊に供える水の一滴になり得るのならと思い、これを鎮魂歌として形に残しておこうと決めました。
自分の親の世代にとっては辛い記憶が身近過ぎる事等もあって、私は被爆した親族について、ごく大まかな事しか聞いたことがありません。時の流れに従えば、父方の祖父母や曽祖父母があの日経験した事を知る人は、数十年後にはもういないかも知れません。彼らに起きた事がなかった事にされない為に、あの日を境に「いなかった者」として消されない為に、この歌と共にその名を記しておきます。
前述の通りこの鎮魂歌は詩ではなく、万葉集にも収められた長歌という形式のやまとうたです。古語を多く用いた歌の原文は解りにくいので、幅広い人が読み易いように現代語の訳文を付けました。呪文のようで取っ付きにくい長歌ですが、もし良ければ声に出して読み上げて下さい。歌は強い力を持ったことばなので、その声は亡き人にも届くかも知れません。
令和6(2024)年8月
著者親族の被爆記録
1.著者の父の父・中原庄市は、1910年に山口県阿武郡高俣村(現萩市むつみ地区)
高佐・横坂に生まれる。若くして単身広島に出て、印刷所「行進社」を経営。
結婚後、妻・澄の両親の山本八助、ミサヲ夫妻と共に広島市雑魚場町(現中区国泰寺町)に住んでいたが、大戦末期に家は建物疎開で取り壊され、強制立ち退きとなった(雑魚場町一帯では、8月6日に非常に多くの学生が建物疎開作業に動員されて亡くなった)。家を追われた後、庄市と妻子は山口の故郷へ疎開し、八助夫妻は市内の近く(戸籍には「平野町へ転居」とあるが不明)へ移った。
原爆投下の一報を受けた庄市夫妻は、妻の両親を探しに投下直後の広島に入り被爆。市中心部は一面がれきの山で、家にあった赤い三輪車を見つけてようやく両親宅の場所が分かったという。8時15分に広島駅にいた八助は、火傷などを負いながらも一命を取り留めたが、ミサヲ(当時54歳)の消息は一切不明。
1952年、庄市の一家は子供たちに高等教育を受けさせる為に広島に戻る。庄市は広島で児童雑誌「ぎんのすず」の印刷を担当していたが、被爆の9年後に末期の骨肉腫が見つかり、すぐに亡くなった。後に遺された妻子六人は貧窮の生活を余儀なくされ、澄は被爆の20年後に49歳で逝去。(著者やその父たちの本籍地は、今も国泰寺町のまま。八助とミサヲは死亡届も出されず、戸籍の上では近年まで生きていた。)
2.著者の母の父・妻苅豊は、消防署の職員として現在の東区牛田本町にて屋外作業中に被爆。建物の陰で火傷は免れたが、ガラスの破片を受け、柱の下敷きになるなどして胸や頭を負傷。徒歩で東区戸坂の自宅に何とか辿り着いた際には、全身血だらけで家人も誰だか分からなかった。戸坂には、市内からたくさんの被爆者が逃れて来て救護所が設けられ、そこで亡くなった人も多数あった。豊の自宅でも被爆者を一人、しばらく救護していた。
3.妻苅豊の姉の娘・前田雪枝は、アメリカに家族が渡った後で大戦が勃発したために、家族の元へは行けず、母親の実家に身を寄せていた。被爆当日は、現中区上八丁堀の大蔵省広島財務局に出勤していて、消息は一切不明。享年21歳。
4.豊の妻の妹・杉本ヒサエは、現在の安佐南区中須在住。当日体調の悪かった人に代わって、現中区加古町付近の建物疎開作業に出て被爆。当時28歳で、消息は一切不明。安佐南区川内地区などからは、多くの人が建物疎開に動員されて被爆したという。